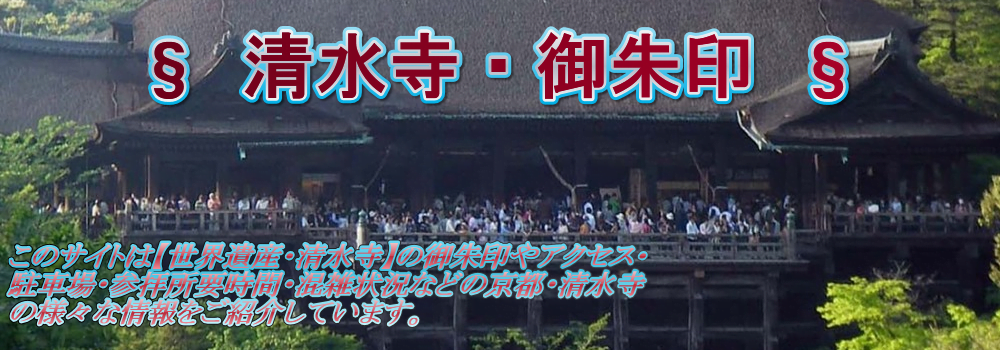京都・地主神社の歴史(年表)
神代・縄文時代
| 年 | 歴史 |
|---|---|
| 神話の時代 | 創建、土地神として信仰をあつめる。 |
飛鳥時代〜奈良時代
| 年 | 歴史 |
|---|---|
| 701年-788年 | 地主神社本殿の建立。地主神社本殿は法隆寺(奈良)でも見られる日本最古の神社建築様式ともなる双堂建築を採る。 |
| 797年 | 坂上田村麻呂が征夷大将軍に任命され、大刀一振りを地主神社に奉納す。 |
平安時代
| 年 | 歴史 |
|---|---|
| 811年 | 嵯峨天皇が行幸(みゆき/天皇がおいでになること)。 *桜の美しさに三度を返されたことから「御車返しの桜」との呼び名がつきました。 |
| 970年 | 3月9日、円融天皇が行幸。 *臨時祭をお命じになり、それが、現在の例大祭「地主祭り」の元となっています。 |
| 1082年 | 白河天皇が行幸す。 |
| 1170年 | 後白河上皇篇の「梁塵秘抄」に地主神社の記述が見られる。毎年三月、白川女により地主桜を御所に献上。 ※白川女=四季の草花を頭上に載せて京都市内を売り歩いた女性のこと。 |
鎌倉時代
| 年 | 歴史 |
| 1202年 | 運慶、狛犬一対奉納。梶原景清が参拝。 |
室町時代
| 年 | 歴史 |
| 1500年 | 連歌師の宗祇(そうぎ)が地主連歌を興行。 名桜・地主桜が「閑吟集」に詠まれる。 世阿弥作の謡曲「田村」ならびに「熊野」でも地主桜が謡われた。 |
| 1581年 | 3月、豊臣秀吉が地主神社にて花見の宴を催す。 |
ちょぃと下掲。画像をご覧くだせぇ。
この画像は室町時代に描かれたと伝わる「清水寺参詣曼荼羅」と呼ばれる絵図になる。
さて、地主神社はドコにあるのか?お分かりになりますけぇの?(タップで拡大可能)
‥‥‥
‥‥‥正解はココ!1.2.3‥👇
 ⬆️上掲画像は1548年(天文17年/室町時代)作とされる清水寺参詣曼荼羅
⬆️上掲画像は1548年(天文17年/室町時代)作とされる清水寺参詣曼荼羅
江戸時代
| 年 | 歴史 |
|---|---|
| 1633年 | 徳川家光公が現存の社殿を再建。 |
| 1705年 | 北村季吟・室井其角、地主の桜の俳句を奉納。 |
| 1779年 | 後桃園天皇崩御につき、地主祭りが5月8日となる。 |
| 1789年 | 光格天皇が鶴亀松竹梅模様の酒器(瓶子:へいし)を奉納される。 |
| 1822年 | 清水寺成就院蔵海が本殿屋根を修復す。 |
| 1849年 | 古文書に地主神社の乙羽竜神の加護により、さる商人が無事に唐土(中国)より帰国できたと記す。 厄除子孫繁栄の守り神としてますます信仰を集めたとある。 |
| 1857年 | 有栖川宮幟仁親王(神道教導職総裁)が地主神社へ「地主権現」の神号を真筆され奉納す。 |
| 1869年 | 有栖川宮熾仁親王筆「地主権現」神号を寄付。政府より「明神号」が下付される。 |
| 1870年 | 神仏分離令ならびに上知令により清水寺の寺領が没収される。その後、清水寺成就院より地主神社に対し毎年米2石助成の嘆願あり。 |
| 1871年 | 地主の桜、禁裏御所への献上を一時中止。 |
| 1878年 | 神幸祭の祭日を4月7日から5月8日に改める。 |
| 1881年 | 12月12日、昇格報告祭(明神号)。社詞・中川義郎。 |
| 1896年 | 6月4日、内務大臣・板垣退助へ由緒下付金を申請。 |
明治時代
| 年 | 歴史 |
|---|---|
| 1868年 | 明治政府の神仏分離令により、地主権現社が「地主神社」として分離独立。 |
昭和・平成時代
| 年 | 歴史 |
|---|---|
| 1966年 | 6月、地主神社本殿、拝殿、総門が国の重要文化財に指定。 |
| 1975年 | ご本殿、拝殿、総門、昭和の大修理。 |
| 1993年 | 地主神社境内地全域が、重要文化財に指定。 |
| 1994年 | 12月、ユネスコの世界文化遺産「古都京都の文化財」登録される。 |
| 1999年 | 神社本教(京都周辺の旧民社を中心とする神社が加盟)の主管(代表)に当社の宮司が就任す。 |
京都・地主神社の創建年
地主神社の社伝によれば、神代(かみよ)の時代(日本国ができる前)に創建されたとされているが、詳しい創建年は判然としない。
神代ということは、神話の時代(日本においては天地開闢より神武天皇即位までの時代)にはすでに存在していたことになる。
飛鳥時代(701年)には社殿や祠などがすでに当地に建っていたとされるが、788年に坂上田村麻呂将軍が清水寺の鎮守社として創建したという説もある。
ちなみに「鎮守社」とは、寺などを祀る(守護する)神社のことを云ぅ。
地主神社の”とある遺物”が創建説の裏付けとなっている
アメリカの原子物理学者・ボースト博士が当地に来訪した際、 本殿前の「恋占いの石」の調査が実施され、縄文時代の祭祀遺物であることが明らかにされた。
祭祀遺物ということは縄文時代、当神社周辺に何らかの祭祀の場所や集落があったことを意味する。
縄文時代ということは、はじめ人間ギャートルズ🦴 or ボンキュボンレディ💋を追いかけ回す💕かの如く、シカやイノシシを追いかけ回して、狩りをしながら生活していたような大昔。…なんとなく言いたいこと分かるけど、‥総じて意味不明
地主神社の周りは海だった?
この石が縄文時代のものだと分かったことから、さらに調査が進められ、なんとぉぅっ!驚くことに神代の時代、地主神社の周りは湖だったことが明らかにされ、さらにぅぃ、
地主神社の東隣下の崖には船着場があったことも明らかにされた。
さらに調査が進められると、神話の時代、地主神社が建つ場所は小島だったことも明らかになり、その当時、中国の仙境に比定される不老長寿の「蓬莱山(宝来山)」 として信仰されていた説も浮上した。
奈良時代
778年になると清水寺が現在の音羽の滝に面した音羽山の尾根に築かれることになり、以降、地主神社は清水寺の鎮守社となる。
地主神社は元来、かつて京都内(山城国)に存在した愛宕郡(あたぎごおり)也佐加郷(八坂郷)の産土神とされ、古くから東山周辺の鎮守神として信仰があった。
坂上田村麻呂も征夷大将軍に任命された折、太刀一振りを当社へ奉納していぃ‥‥‥申す。しばらく無かったら‥ダメね♡やっと出番キタわ…ギャホェっ (興奮しすぎて”いぃ”なっとる)
田村将軍は征夷大将軍を襲名した後、朝廷郡を率い蝦夷平定へ赴くことになり、その結果、見事に蝦夷平定を成す。
凱旋後、蝦夷民族に大勢の死者を出したことから、その御霊を鎮めるために清水寺を創建したという説もあるが、定説ではすでに建っていた清水寺を増築したとされる。
関連記事:![]() 京都・清水寺の歴史(年表)
京都・清水寺の歴史(年表)
江戸時代に境内社殿が一新される
当社境内に現存している社殿群は、田村将軍以後の系譜となる征夷大将軍・江戸幕府3代将軍の徳川家光公によって1633年(寛永10年)に再建されてい‥‥‥申す。ダファギャフェっ
なお、家光公(江戸幕府)による再建計画は当社だけではなく、清水寺を中心に実施された。
激動の明治時代が当社を襲う
明治時代初頭、政府より神社とお寺を切り離す命令(神仏分離令)が発布されることとなり、清水寺は地主神社の切り離しを余儀なくされる。
その後の1868年(明治元年)、音羽の滝に奉斎されていた神道の神である「滝明神(龍神)」や栗光稲荷を地主神社へ遷す(うつす)計画が成り、同時並行で清水寺の所属から離れた独立した神社となってい‥‥‥申す。ちょっと休憩しょか..オホっ
なお、実は江戸時代以前の地主神社の境内には「地主権現」として「文殊菩薩」が奉斎されており、この文殊菩薩は現在、清水寺本堂の御本尊脇の厨子の中に奉安されてい‥‥‥申す。ちょぃ発動見送り(今エエとこ。オホ …何がや)
1994年(平成6年)に世界文化遺産に登録される!
地主神社にとって大きな出来事となったのが、1994年(平成6年)に清水寺とともに世界遺産「古都京都の文化財」に登録されたこと。
登録理由は、『歴史的経緯から清水寺の一部』とみなされたことによるもの。うきゃきゃ
現在の地主神社
地主神社は縁結び💕の神として名高い島根県出雲大社の神として有名な大国主命(大国主大神)を祭神として奉祀している事実や、江戸時代に上述の縄文時代の石が「恋占いの石」として人気を博した背景もあり、その様相が現在にまで踏襲されると「恋愛成就の神社」として有名になった。
江戸期に再建された社殿とはなるが、それ以前の奈良時代の建築様式を伝える神社としても今日、世界遺産の構成資産として世界中にその名が知られてい‥‥‥申す。タワシ ハ キクロンっ
京都・地主神社が世界遺産された理由とは?
地主神社は奈良時代より清水寺の鎮守社になったため、以後は清水寺を取り巻く様々な諸問題とも直面するなど、その歴史の変遷は平坦には収まらず、むしろ紆余曲折にまみれた。
しクぁし!清水寺中興の祖として知られる大西良慶和上のご活躍もあり、京都清水寺の名前が世界に広まると、1994年「古都京都の文化財」に清水寺が世界文化遺産として登録を受ける運びとなり、清水寺と運命共同体にあった京都・地主神社もその恩恵を大いに受けて隆昌した。
現在の地主神社境内は以下の建造物が世界遺産登録されてい‥‥‥ます。(フェイント)発動くると思った?フフっ
世界遺産登録されている建造物一覧
- 本殿
- 拝殿
- 総門
- そのほか境内
なお、世界遺産に登録されている「古都京都の文化財」とは、17の神社・寺院・城で構成されているものです。
地主神社の桜は「地主の桜」と謳われた京都屈指の名木
室町時代に成立したとされる能・謡曲の「田村」、歌謡集の「閑吟集(かんぎんしゅう)」や、著名な謡曲「湯谷(熊野)」でも平宗盛の撰にて花見・酒盛り宴の場所とされた様が歌われているが、これらに共通するのが「”地主の桜”」が登場すること。
地主権現の花盛り、面白ろの花の都や、花の名所多しといえども、この寺の地主の桜にしくなし (湯谷)
地主の桜の前での宴の席では法楽・連歌会が催されるなど、まさに京の華の象徴ともなった。
地主からは木の間の花の都哉(かな) 北村季吟(きぎん)
京中へ地主の桜や飛ぶことふ(胡蝶) 榎本其角(きかく)
関連記事一覧
スポンサードリンク -Sponsored Link-
当サイトの内容には一部、専門性のある掲載がありますが、これらは信頼できる情報源を複数参照して掲載しているつもりです。 また、閲覧者様に予告なく内容を変更することがありますのでご了承下さい。