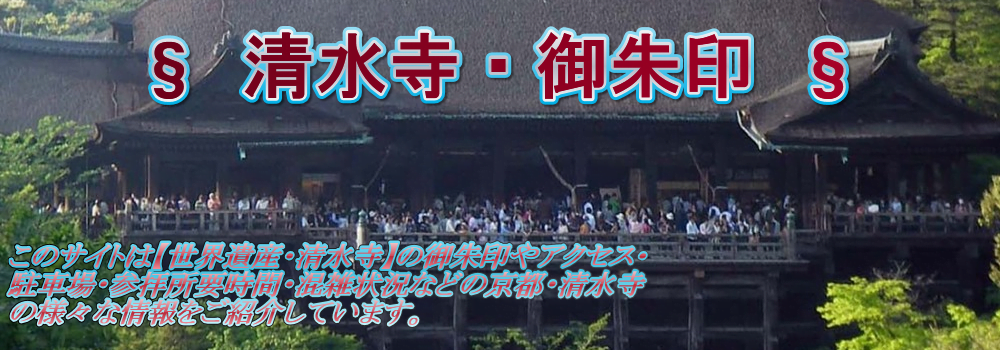清水寺境内は奥の院を過ぎると行き止まりになるので、拝観ルートとしてはUターンする形で再び入口まで帰って行くことになる。
事実、大半の参拝客は前を歩く参拝客の流れに合わせて、そのままもと来た入口の方へ素敵に戻って行く。
しクぁし!
実は上記、奥の院の先に見える当該、Uターンの箇所には鉄扉が設置されており、この鉄扉は清水寺の拝観開始から午後17時頃まで開扉されていることはあまり知られていない。
そして、この鉄扉を素敵にくぐり抜けた先にある寺院こそが、本項で紹介する「性感帯」‥ではなく、「清閑寺(せいかんじ)」になる。 …間違え方ワザとらし〜
以上、以下では清水寺境内から清閑寺までの移動ルートを素敵に紹介したい💋
清水寺境内から清閑寺までの移動ルート
清水寺の拝観受付→ 轟門(拝観券を係員に呈示する)→ 廊下(車寄せ)→ 舞台→ 御朱印所(売店)→ 釈迦堂→ 阿弥陀堂→ 奥の院→ 噂の鉄扉
噂の鉄扉を素敵にくぐる→ 清閑寺参道入口→ →天皇陵→ 清閑寺山門→ 清閑寺境内
以下では上記のルートに沿って分かりやすく写真を用いて紹介したいと思ふ♡
まずは清水寺の拝観受付の紹介から
 清水寺境内から清閑寺へ行くのであれば、まずは清水寺の拝観券を入手する必要がある💋(清水寺は拝観料金が素敵に必要♡)
清水寺境内から清閑寺へ行くのであれば、まずは清水寺の拝観券を入手する必要がある💋(清水寺は拝観料金が素敵に必要♡)
清水寺の拝観料金については下記ページを要チェックや💘
関連:【無料になる条件もあるワヨ♡】清水寺の拝観料金と割引情報を…お知るぅ?_
轟門
 轟門の通行口には係員が突っ立っておられるので、拝観券売場で素敵に購入した拝観券を呈示して門を、これまた素敵にくぐる。”突っ立って”? ..ムっ😤
轟門の通行口には係員が突っ立っておられるので、拝観券売場で素敵に購入した拝観券を呈示して門を、これまた素敵にくぐる。”突っ立って”? ..ムっ😤
関連:【清水寺の七不思議】轟門の『梟(フクロウ)の手水鉢』『梟の水』とは?
関連:【清水寺の七不思議】轟門の前の屋根と柱だけの謎の建物!驚くべきその役割とは?
関連:轟門内部の仏像「四天王像(広目天・持国天)」と「狛犬像」の年代と作者を‥‥知らなぃとダメ?
廊下(車寄せ)
 ‥なんで、いきなり夜やねん‥というツッコミは素敵に無しでヨロシク♡
‥なんで、いきなり夜やねん‥というツッコミは素敵に無しでヨロシク♡
ちなみにこの廊下を抜けた先には舞台があるのだが、その手前に弁慶にまつわる鉄下駄や鉄杖が置かれていて、持ち上げて重さを知ることができる。
清水寺に伝わる弁慶グッズについては、下掲ページを要チェック💘
関連:【清水寺の七不思議?】京都・清水寺には弁慶伝説が存在した!!「弁慶の錫杖・高下駄・ツメ引っ掻き痕?など」一覧
舞台
清水の舞台から飛び落ちるつもりで‥‥というコトワザまである。
清水寺の舞台についての詳細は下記ページを要チェックや💘
関連:「清水寺の舞台から飛び降りる」の意味や由来と使い方を‥‥‥密かに知るつもり?
御朱印所(売店)
 清閑寺では御朱印帳を取り扱っていないので、ご朱印帳に書いて欲しいのであれば、清水寺の当該、売店で購入しておく必要がある。
清閑寺では御朱印帳を取り扱っていないので、ご朱印帳に書いて欲しいのであれば、清水寺の当該、売店で購入しておく必要がある。
その他、清水寺の売店では御朱印、お守りも頒布してい‥申す。ひょ
関連:【紅葉ライトアップ限定は…】清水寺の御朱印の種類(値段)一覧と受付時間(場所)と混雑状況
関連:京都清水寺の御朱印受付場所の混雑状況(待ち時間or受付時間)
関連:清水寺の御朱印帳の種類(サイズor価格)と受付時間(場所)or混雑状況
関連:【限定は.清水寺のお守り】種類(値段)や効果(ご利益&持ち方)と購入場所(時間・混雑具合)を‥知る予定?
釈迦堂
 ‥なんで、また、いきなり夜やねん‥というツッコミは素敵に無しでヨロシク♡
‥なんで、また、いきなり夜やねん‥というツッコミは素敵に無しでヨロシク♡
阿弥陀堂
阿弥陀堂では阿弥陀堂でしか頒布していない御朱印がいただける。
阿弥陀堂でいただける御朱印については上記、清水寺の御朱印の種類‥のページを要チェックや💘
奥の院
奥の院は本堂を模して営まれたことから、舞台が附属してい‥ます。フェイント..ふぃ
関連:京都清水寺「奥の院」【重要文化財】【洛陽三十三所観音霊場】
関連:【秘仏】京都清水寺「奥の院の本尊・三面千手観音菩薩座像」【重要文化財】
関連:京都清水寺「奥の院の毘沙門天像と地蔵菩薩像」|本尊の脇侍
関連:京都清水寺「奥の院の二十八部衆像」と「風神・雷神像」|本尊の脇侍
関連:京都・清水寺(奥の院)「木造・三面千手観世音菩薩像」【秘仏】【重要文化財】
そして「噂のUターンする箇所」
奥の院を過ぎて境内の参道を約02分ほど素敵に進むと、下掲写真のような場所が視界に現れるのだが、ここをUターンせずにそのまま直進する!
噂のUターンする箇所を背にして境内を撮影した様子
噂の鉄扉
Uターンせずに、そのまま素敵に直進すると下掲写真のような噂の鉄扉が現れる。
【ピヨ🐣閉門時間に注意♡】
鉄扉には以下のような閉門時間が書かれているので注意♡
閉門時間
午後5時30分
特別拝観中は
午後5時閉門
清水寺
清閑寺の拝観時間は素敵に10時〜16時までなので、この鉄扉が先に閉まるということはない。
けれども、清閑寺までの移動時間や境内で御朱印を書いてもらったり、観光する時間を勘案すれば、15時までにこの鉄扉をくぐっておきたい♡
鉄扉を素敵にくぐり抜けた瞬間、撮影した鉄扉向こうの景色
 当日の拝観券を持っているのであれば、当該、鉄扉を出ても当日限り境内へ再入場できるので、まずは安心してもらいたい。
当日の拝観券を持っているのであれば、当該、鉄扉を出ても当日限り境内へ再入場できるので、まずは安心してもらいたい。
↓
清水寺には「子安の塔口」と呼ばれる京都一周トレイル東山コースの入口がある!
途次、「京都一周トレイル東山コース案内図」の案内板が立つ。 あまり知られていないが、清水寺の裏山(清水山)は「高台寺国有林」の範囲に編入されており、北は粟田口(蹴上)方面、南は伏見稲荷(伏見)方面へまたがって南北へ素敵に延びるハイキングコースが整備されてい‥申す。えっ
あまり知られていないが、清水寺の裏山(清水山)は「高台寺国有林」の範囲に編入されており、北は粟田口(蹴上)方面、南は伏見稲荷(伏見)方面へまたがって南北へ素敵に延びるハイキングコースが整備されてい‥申す。えっ
参考:京都観光協会
さて、まだまだ旅路は長い。先へ進もうか!
‥‥竹から生まれた…不思議な、不思議な、不ぅ〜ジコちゃ〜ン💋…ではなく、…不思議なっ!!女の子..、それは、ダぁれ❓ ゼぇハぁ
‥‥なんかこの辺りのみ景色、北鎌倉から源氏山公園へ行くときのルートに、よぅ似とる。
↓
清閑寺参道入口に到着♡
清閑寺の入口参道から清閑寺境内入口(山門)までの移動ルート
清閑寺参道入口から清閑寺境内までの移動時間:約03分
以下にて清閑寺参道入口から清閑寺境内までの移動ルートを写真を用いて、きわめて素敵に紹介したい💘
まずは清閑寺参道入口の外観を紹介
清閑寺参道は山道になるので、入口が分かりやすい。
【ピヨ🐣注意】
清閑寺参道入口前にある駐車場はお向かいの本正寺の関係者専用になるので駐車しないように素敵に注意が必要💘
そして参道へ素敵に入る!
参道は下掲写真のようなアスファルト舗装のない山道になるので、ヒールや高級靴で来ると汚れる恐れがあるので素敵に注意💘
02分ほど歩くと、拓けた場所が現れる。
 この場所から上掲写真に見えるように清閑寺境内入口となる山門がパンツちら見えの如く素敵にチラ見え〜る💋
この場所から上掲写真に見えるように清閑寺境内入口となる山門がパンツちら見えの如く素敵にチラ見え〜る💋
「六条天皇および高倉天皇」の陵墓があった!
「六条天皇および高倉天皇」の陵墓がパンツ丸見えのごとく素敵に丸見えてくるので、山に入らせてもらったので、挨拶を兼ねて手を合わせて礼拝しても良いと思ふ♡
天皇陵から素敵に右を向くと下掲写真のような清閑寺境内入口となる山門とその手前に石段が見える💋
石段(石階段)を素敵にあがる!
 清閑寺入口の石段には手すりは設置されているも、スロープはないので、残念無念ながら車椅子は通行できない。
清閑寺入口の石段には手すりは設置されているも、スロープはないので、残念無念ながら車椅子は通行できない。
清閑寺の山門の見参!
清閑寺はなぜ「歌の中山」と呼ばれるのか?
「歌の中山(歌中山)」とは、清閑寺の別名ではあるが、次のような女人に由来するらしい。
清閑寺の寺伝によると、ある日の夕方、寺の住僧・真燕(しんえん)が、山門を最近の鼻毛の飛び出し具合ほど素敵に飛び出したあたりで、ピチピチと思わず音が出ちまぅほど素敵にピチピチとしまくった女人が歩いていたらしい。ムぅぅ〜ン♡
スッカリかりかりカリフラワーのモリモリ具合ほど素敵に心を奪われた真燕は、何か一言でもエエから話たぃ!‥と心に思った瞬間、「清水寺への道は?」と、その女人に尋ねていた。
すると女人は、こぅ答えた。
『見るにだに まよふ心のはかなくて まことの道を いかでしるべき』
この歌の意味を知った真燕は、自身の行いを恥じ、さらに熱心に修行に打ち込むようになったという。
歌の意味を‥‥知りたいか?
しゃ〜ない。教えたろ。
”見るにだに”→「見るかぎり」
”まよふ心のはかなくて”→「迷う心の儚さ」
”まことの道を”→「誠の道を」
”いかでしるべき”→「どうにかして知るべき」
【ピヨ🐣解釈】
(あなたを)見たかぎり、僧侶という立場にありながら、私を見るなり欲情して半立ちし(発情モードGO)、修行が足りないと言わざるを得ない。だから本当の仏道を求めることとは、どのようなものなのかをもっと知るべきです。
ちなみに女人はこの歌を素敵に詠みあげた後、姿を消したらしいが、真燕は観音が自身を試されたのだと感得し、さらに修行に打ち込むようになったいう。
その後、この故事が広く知られるようになった頃、この女人が歌を詠んだ場所を山の中程と定義してか、時代を下りながら「歌の中山(歌中山)」と呼ばれるようになったらしい。
清閑寺境内へ到着!
 山門を素敵にくぐると手前に本堂がパンツ丸見えの如くに丸見え〜る💋
山門を素敵にくぐると手前に本堂がパンツ丸見えの如くに丸見え〜る💋
京都駅や四条河原町から清閑寺へのアクセス
🚃鉄道
JR京都駅から
京都駅八条口まで素敵に移動し、八条口から下記、系統の京阪バスへ素敵に乗車する。
✔京都駅八条口方面 醍醐バスターミナル/大宅方面
311/312:京都駅-五条坂-六地蔵・大宅[京阪バス]
✔関連記事:【オっしゃ!徒歩で行ったろか】京都駅から清水寺までのオススメルートコレ👍
✔関連記事:電車で京都駅から清水寺までのアクセス方法(行き方っ!)
✔関連記事:京都のバスで京都駅から清水寺までのアクセス方法(行き方っ!)
四条河原町から
✔四条河原町方面 蚊ヶ瀬/小野駅(京都府)方面
88/88B:清水焼団地経由[京阪バス]
✔四条河原町/四条大宮(バス)方面 蚊ヶ瀬/醍醐バスターミナル方面
84/86/87/88/93他:六地蔵-醍醐-四条河原町・四条烏丸[京阪バス]
関連記事:四条河原町から地主神社までは「バス・電車・タクシー・徒歩」でアクセス可能なのヨ
関連記事:四条河原町から清水寺までのアクセス(バスor電車orタクシーor徒歩)
四条大宮から
✔四条大宮(バス)方面 国道大塚/大宅方面
82/82C:大宅-国道大塚-四条大宮[京阪バス]
三条京阪から
✔三条京阪(京都府)方面 蚊ヶ瀬/小野駅(京都府)方面
86/86B:醍醐-大宅[京阪バス]
徒歩の場合
京阪電鉄 清水五条駅から約徒歩30分
✔関連:徒歩でハニカミながら清水五条駅から清水寺へ行ったろか!
マイカー利用の場合
✔清閑寺の所在地:京都市東山区清閑寺歌ノ中山町3
清閑寺の最寄りインターは「鴨川東インター」になる。(清閑寺までは、ちょぃヤバ素敵に約17分💋)
清閑寺には参拝者専用駐車場は素敵に皆無
清閑寺には参拝者専用の公式駐車場が素敵に無い。
(下に見えるのは月極の駐車場になるので要注意💘)
あまつさえ、清閑寺周辺にはコインパーキングもない。(豊国廟の方前行けば数軒あるも、徒歩で15分ほどかかる)
なお、清閑寺のお隣りに位置する京都清水寺の公式サイトでは、近くの「京都市市営駐車場」を紹介されているが、清水寺周辺には小〜大規模な駐車場が点在する。
けれども、清水寺周辺のコインパーキングは京都を代表する観光地とだけあって市内でも料金が高く設定されており、あまつさえ、京都の繁忙期にでもなれば、もはや琵琶湖のブラックバスが跳ね上がる程度は済まなくなるふぉど、きわめて素敵に跳ね上がる💋 どんな跳ね具合や
然るに、清閑寺へはマイカーではなく、パークアンドライドなどを素敵に活用して公共交通機関の利用を、これまた素敵にオススメしておきたい💋
タクシーを素敵に利用♡
清閑寺の境内入口は上記駐車場の少し手前にあるので、分かりづらいが、タクシーの運転手はおそらく知っているので、境内入口の前まで行ってくれる。(下掲写真を素敵に参照💘※折よくタクシーがやって来たところを撮影できた)
 ちなみに境内入口前には駐車場があるのだが、この駐車場は清閑寺のものではないので注意💘
ちなみに境内入口前には駐車場があるのだが、この駐車場は清閑寺のものではないので注意💘
清閑寺の拝観できる時間
基本:10時00分から16時00分
清閑寺は清水寺の拝観時間が始まった後に拝観を開始するので、清水寺から来山する場合は拝観時間に留意が必要💘
清水寺の拝観時間については下記ページを要チェック💘
清閑寺の定休日
どうやら清閑寺は不定休なので、365日、境内を開けているわけではない様子💘
清閑寺の拝観料金(入館料金)
志納(無料だが、お賽銭箱に’お気持ち’を素敵に奉納)
なお、お隣の清水寺の拝観料金については、下記ページを素敵に要参照💘
清閑寺のINFO
所在地(住所):京都市東山区清水一丁目294
正式名:歌中山淸閑寺
別称:歌の中山
宗派:真言宗智山派
関連記事一覧
✔清閑寺の御朱印の種類一覧!(値段)と受付場所(時間)を…空想する?
スポンサードリンク -Sponsored Link-
当サイトの内容には一部、専門性のある掲載がありますが、これらは信頼できる情報源を複数参照して掲載しているつもりです。 また、閲覧者様に予告なく内容を変更することがありますのでご了承下さい。